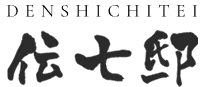伝七邸について

明治29年(1896年)から第十世伊藤伝七翁の住居だった伝七邸は、明治39年(1906年)から平成29年(2017年)3月まで料亭浜松茂として皇室関係者や政財界から愛される迎賓館的な存在となり、四日市の象徴であり続けました。

2017年に迎えた存亡の危機
しかし、120年余り繁栄し続けた伝七邸(料亭浜松茂)は建物の老朽化と後継者不在のため、その歴史の幕を閉じることになったのです。

そこで、この地の再建に乗り出したのが、
11代目九鬼紋七でした。
伊藤伝七と同じ時代に四日市の発展に尽力した九鬼家。その11代目九鬼紋七は、伊藤伝七の志を次世代に継承するために、人と文化が交流する料亭を目指し「伝七邸」を再開業しました。
伊藤伝七と同じ時代に四日市の発展に尽力した九鬼家。その11代目九鬼紋七は、伊藤伝七の志を次世代に継承するために、人と文化が交流する料亭を目指し「伝七邸」を再開業しました。
国の登録有形文化財
建物のうち、玄関棟とさつき棟は国の登録有形文化財として登録されています。

参考文献
「10世伊藤伝七の幅広い活動」吉村利夫(三重大学社会連携特任教授 三重県歴史編集委員)
「日本経営の巨人伝13―わが国紡績会の創始者・三重財界の重鎮の伊藤伝七」前坂俊之(静岡県立大学名誉教授)
「東洋紡の成立:三重紡・大阪紡の合併交渉」橋口勝利[関西大学経済論集,66(1):31-46]
伝七邸の歴史
| 明治29年(1896年) | 第十世伊藤伝七翁により、四郷村室山町の本宅に対して別邸として建築される。 玄関棟が建築される。 |
|---|---|
| 明治33年(1900年)頃 | 昌栄館の館号として、渋沢栄一など四日市訪問中の名士を招く宿泊や会合の場所として提供されていた。 |
| 明治39年(1906年) | 料理人であった吉田氏に所有権が移り、料亭浜松茂(浜の松茂楼)となる。 |
| 昭和20年(1945年) | 四日市大空襲に耐え、建物が残る。 |
| 昭和26年(1951年)頃 | さつき棟が建築される。 |
| 昭和26年(1951年)11月 | 昭和天皇の戦後行幸の際に、隣接する伊藤伝七のご自宅「昌栄館」(現在は滅失)を行在所(宿舎)として提供。 |
| 昭和34年(1959年) | 伊勢湾台風による被害。 |
| 平成22年(2010年) | 玄関棟、さつき棟の2棟が国の登録有形文化財となる。 |
| 平成29年(2017年)3月 | 料亭浜松茂が廃業 |
| 平成29年(2017年) | 11代目九鬼紋七が継承 |
| 平成29年(2017年)6月 | 「伝七邸」(建物名は旧伊藤伝七別邸)に名称を変更して修復作業開始。 |
| 平成29年(2017年)12月 | 飲食部門を営業開始 第1期改修工事完了式典を開催。 |
| 平成30年(2018年)12月 | 展示会 萬古焼作家10人による「沼波弄山翁 生誕300年記念 四日市萬古作家協会展」を開催。 |
| 令和元年(2019年)5月 | 伝七邸創建123周年記念 料理界の巨匠熊谷喜八、四日市萬古焼の名工清水醉月 賞味会を開催。以降、熊谷喜八氏を迎えての賞味会を定期的に開催。 |
| 令和元年(2019年)9月 | 展示会 萬古焼作家10人による「四日市萬古作家美術展」を開催。 |
| 令和元年(2019年)10月 | 四日市市制施行123 周年記念市民企画イベント 和の文化祭「和の煌き」~花・書・茶・染・陶~を開催。 |
| 令和元年(2019年)11月 | 展示会 陶と大和絵の二人会(陶芸榊原勇一、大和絵小川康子)を開催。 |
| 令和5年 (2023年)4月 | 小さな北欧美術館“アンネ・パソ展”を開催。 |
| 令和5年 (2023年)12月 | 四日市の酒蔵×四日市の萬古焼との饗宴~よっかいちガストロノミー~を開催。 |
| 令和7年 (2025年)1月 | 「津みやび」(株式会社グリーンズ)とコラボレーション企画第1弾”黒毛和牛ロース炙り焼き肉重膳”を津みやびで限定販売。 |
| 令和7年 (2025年)3月 | 定期開催「伝七邸 邸主と美酒を楽しむ会」がスタート。 |
| 令和7年 (2025年)4月 | 落語独演会を開催。 出演:三遊亭楽生 |
| 令和7年 (2025年)5月 | 「津みやび」(株式会社グリーンズ)とコラボレーション企画第2弾”黒毛和牛ビーフシチュー御膳” を津みやびで限定販売。 |
その他、お茶会や三味線などの催しや、地域の名士による講演会などを定期的に開催している。